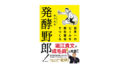ビールの自作はできないけど、翻訳されたビールのつくり方の本を読むと、モルトにはいくつも種類があり、ビール酵母もたくさん種類があることが分かります。ビール好きならこの本はとても面白く読める本だと思います。

世界に通用するビールのつくりかた大事典を読みました。
昨年、2回ほどビール工房に行ってエールビールを飲みました。昔、1990年代から地ビールはありましたが、当時の地ビール工場はとても大きかったです。
しかし、現在は、お店で醸造できるくらい醸造量が少なくても許可?が下りるようになったのでしょう。地ビールでなく、クラフトビールといわれます。実に楽しそうな(うらやましい)仕事です。
そんな時代だからでしょうか。このようなビール好きにはたまらない本が出版されるのは。この本は、ビール好きが書店で手に取ったら思わず買ってしまう本だと思います。
著者について
ぼくの名はジェームズ。イギリスではパン焼き職人として、そして楽しいことなら何でも首をつっこむヤツとしての顔のほうがよく知られています。
これまでの2冊の著書『Brilliant Bread(パンはすごい)』と『How Baking Works(パン焼きの化学)』を書いていたときもそうでしたが、まあ、とにかくいつでも何かの醸造にいそしんでいます。
作業をするのは自分の家のキッチン。ビールづくりでやっかいなのは、いったん醸造を始めたら最後、ほかのことはもうどうでもよくなってしまうことです。
もし誰かがビールについて語りはじめたら、会話を乗っ取ってしまうでしょう。あるいは自分と同じようなビールマニアの存在をかぎつけようものなら、知る人ぞ知る野生酵母の長所と短所について、ここぞとばかりに大まじめで討論を展開するはずです。
ぼくが強く興味をそそられたのは2つの点でした。ビールという気軽な飲みものが秘めた可能性、そしてその背後にある科学です。
醸造中に目にした化学のパワーには驚くばかりでしたが、何よりも夢中になったのは、ビールの発酵工程での酵母の扱いでした。
うまく発酵させられるようになるまでにかなりの時間がかかってしまい、初心者用のキットからまともなビールをつくれるようになるまでに、何度も失敗をくり返しました。
いっそあきらめようかとも思いましたが、この点では親友のオーウェンに感謝するばかりです。
著者はJames Mortonさん。ウイキペディアにも記事がありました。1991年生まれだとか。
Brilliant Breadもアマゾンで販売されていました。親しみやすい雰囲気の方ですね。
もう1冊、How Baking Worksもありましたよ。
最初の自己紹介を抜き書きしたのは、この本の特徴がよく書かれているからです。この本の原題は、「Brew: The Foolproof Guide to Making World-Class Beer at Home」です。家庭で品質のよいビールをつくる方法を紹介しています。
日本では酒税法によりアルコール度数1%以上のビール風飲料をつくることはできませんが、これを読むと、ビールができるまでにどんなことが起こるのか分かるのです。
ビールはバケツで発酵させる
ビール工場に見学に行くと、大きな釜を見せてくれます。何となく(根拠なく)そういうふうに造るものなのだと思っていました。
ところが、家庭でつくる時は、プラスチック製のバケツでつくるというのです。
プラスチック製のバケツ(25~30L容量)とタップ各2個
1個めのバケツはビールを発酵させるための道具、つまり一次発酵容器として使います。フタ付きで、運びやすいよう取っ手の付いたタイプが必要です。
食物を入れても安全な素材で、醸造用につくられたものでなくてはいけません。
タップは、蛇口のことです。
これで急にビールづくりが身近に感じられるようになりました。そうか、漬け物を漬けるのとあまり変わらないのかもしれない。
まず、キットを使う
私はまだ実物を見たことがないですが、ビールづくりのキットが販売されています。最初はこれを使うといいとすすめています。
ビールづくりに慣れない最初のうちはキットビールを何回かつくってみるのが賢明です。キットの缶や紙袋に入った、こってりとしてベタつくシロップを、水と混ぜてバケツで発酵させるのです。
もちろん、キットビールづくりは飛ばして最初から特殊な材料をそろえ、オールグレインビールを一からつくってもいいのです。
でも、最初の数回はできるだけ工程を減らしてシンプルにつくることをお勧めするのには、いくつか理由があります。
まず、キットを使えばビールの出来具合が安定するという点です。キットビールは数多くの工夫と労力の賜物であり、特定のスタイルに忠実なビールがほぼまちがいなくつくれます。
たいていのキットから、ひじょうに良質なビールをつくることが可能です。
こうしてすすめるだけでなく、実際にキットを使ってつくる工程を写真つきで解説しています。さらに、親切なことに、キットビールに著者独自の工夫を加えることでさらに美味しくする方法も書かれています。
オールグレインビールをつくる
キットを使ったつくり方の後には、モルトと酵母、ホップと水だけでつくるオールグレインビールのつくり方が続きます。
ビールづくりのソフトウエア
最初に使う道具について丁寧な説明があります。その最後にビールづくりのソフトウエアが紹介されていました。これは珍しいので書いておきましょう。
なにしろビールの醸造には数多くの計算ごとがつきもの。醸造ソフトウェアがあれば、そんなめんどうな計算をすべて引き受けてくれます。(中略)
お勧めしたいのはすべてが含まれたソフトウェアを1つ選び、ずっとそれだけを使うことです。ソフトウェアに材料とレシピを入力すると、すぐに必要な数値をすべてはじきだしてくれます。
実際に使った材料とレシピをすべて記録できるため、ビールをつくるたびにくらべてランク付けすることができるほか、あとで見直すこともできます。
本には4つ紹介されていましたが、Web上で使用する無料ソフトのみ記録しておきます。
ブリューワーズ・フレンド(Brewer’s Friend)
数値を手動で入力すれば、独自のレシピをつくる、レシピごとに醸造用の計算機を使う、醸造の記録を印刷するなどの作業ができます。

グレイン・ビルについて
グレイン・ビルとは、モルトの種類とその配合率のことです。モルトは発芽大麦です。モルトは(でんぷんとして)糖の供給源であり、また糖化酵素の供給源でもあります。
使うモルトは一種類じゃないんだ
モルトにはいろんな種類があるのだろうと思っていましたが、一種類を使うのだと思っていました。
ところが、大まかに二種類のモルトを使うのだそうです。糖化力のあるベースモルトと、糖化力のないスペシャルモルトを使うのだそうです。
ベースモルト
ベースモルトはビールの主原料です。ほとんどあらゆるビールがペールモルトかラガーモルトを主体としてつくられていますが、ベースモルトはおもしろみのない材料かといえば、そうでもありません。
大半は似たりよったりですが、ブレンドすることによって、どんな色のモルトも、あらゆるビールにすばらしく複雑な風味をあたえます。
こちらは主原料兼、糖化酵素(アミラーゼ)の供給元になります。
スペシャルモルト
風味と色を加えるために使われるモルトで、糖化力はありません。通常、熱湯に浸しておくだけで求める風味を充分に抽出できます。
モルトエキスだけを使ってビールを醸造する人が利用する技術です。抽出液をマッシング中の鍋に入れるだけで済むので、オールグレインビールのつくり手にとっては、最も簡単で手っ取り早い工程です。
こちらは、味つけ用のモルトで、でんぷんを糖に変えてもらう原料でもあります。それぞれのモルトにまた種類がいくつもあり、その組み合わせによってできあがるビールの色や風味を変化させるのだそうです。
酵母について
アルコールをつくるために最も重要な酵母について、本当に懇切丁寧に書かれています。これは一部です。
酵母が増殖するためには酸素が必要です。酵母は細菌ではなく真菌なのでミトコンドリアをもっています。酸素呼吸をすることでエネルギーであるATPをたくさん作ることができます。
増殖時には酸素を供給
醸造酵母であるサッカロミセス・セレビシエは、単細胞の真菌です。ビールをつくる立場から偏った見方をすると、その役割は糖をエタノールに変えることです。
この工程で生まれる炭酸ガスという便利な副産物が、ビールを泡立たせるほか、さまざまなおいしい風味の化合物を生み出します。
ほぼあらゆる生きものがそうであるように、酵母細胞の生きる目的は、食べて繁殖することです。条件付嫌気性生物であるビール酵母は、酸素があってもなくてもこの活動を難なくこなせます。
それでもやはり酸素が豊富にあるときは、ないときにくらべてはるかに早く増殖します。
酸素は、酵母が脂肪酸から新しい細胞膜をつくるうえで必要です。酸素はまた、酵母がマルトース(麦芽糖)を吸収するための分子合成をするうえでも欠かせません。マルトースは、ビールの発酵中に酵母が吸収する糖分の大半を占めています。
そのため、酵母を増殖させたいときは酸素をあたえる必要があります。実際面でいうと、酵母スターターをつくるときには必ず、酸素を充分に供給しないといけません。
自家醸造家にとっていちばん簡単な方法は、酵母スターターを一定の間隔で激しく揺することです。筋金入りのビールマニアには、ともすればマグネチックスターラー(注:容器内に入れた攪拌子を外部磁場によって回転させ、攪拌する装置)を持っている人も多くいます。
この器具があると酵母スターターに絶えず酸素を供給でき、酵母細胞の数をおおいに増やせます。
温度管理も考慮に入れるべき要素です。酵母は、最高で人間の体温に近い37度までの環境でも増殖しますが、こうした高温下では深刻なストレスを受けて、人間でいえば自殺寸前の状態になり、オフフレーバーを大量に発生させます。
そのため、発酵中の酵母は室温ぐらい、つまり18~21度に保つようにしなければいけません。
ただし酵母は発酵中に発熱するため、活発に発酵しているときの発酵容器の温度は周囲より数度上がることがあるので要注意です。
酵母を増やす時と、アルコールをつくらせる時は別です。発酵している最中に酸素を供給すると酵母は元気になり数が増えますが品質が悪いビールになります。
こういう話を読むのが好きです。
発酵中は酸素は不要
発酵が始まってからは、酸素を取りこんでしまうとビールが酸化するという危険を招きます。
発酵が始まった最初の2~3日間に、発酵中のビールを何度もバシャバシャと跳ね上げると、たいへん健康な酵母がたくさん生まれます。
しかしビールはそのうちに、カビや濡れたダンボールのようなにおいのする、茶色いドロッとした液体に成りさがってしましいます。
酵母の種類
自作ビール用としていくつか酵母を紹介し、すすめています。
アメリカン・エールイースト、イングリッシュ・エールイースト、ベルジャン・エールイースト、ヘーフェヴァイツェンイースト、ハイブリッドイースト、そして困り者としてラガーイーストが紹介されていました。
ラガーイースト
ラガーイーストはここまで紹介した酵母とはまったく異なる困り者で、12度を少しでも超えると、ほとんどの酵母がひじょうに不快な味を生みます。
専用の発酵室や自動的に温度制御ができる装置でもない限り、これはやっかいです。ですからいまのところは、ラガータイプのビールづくりにはハイブリッドスタイルの酵母を使いましょう。
普段、スーパーで買ってくるビールはほとんどラガータイプです。スッキリ飲みやすいのが特徴ですが、酵母の取り扱いはとてもむずかしく、冷却設備がないとつくれないことが分かります。
砂糖はアルコール度数を高めるために加える
自家製ビールをつくる時に糖分を加えることについて書かれていました。
グラニュー糖(ショ糖、スクロース)
ビールの風味を変えずに、ドライでアルコール度数の高いビールにしたいときに使うとよいでしょう。特にIPAとダブルIPAに加えると効果的です。
また、少量のモルト化されていないオーツ麦や小麦との相性も優れています。これらの麦が、ドライなビールの味が薄くなるのを防いでくれるからです。
ただし入れる量はグレイン・ビルの10%を超えないようにしましょう。
IPAは、インディア・ペールエールのことです。ウイキペディアに詳しい説明がありますので、そちらをご参照ください。ビールの種類です。
グラニュー糖は、いわゆる砂糖です。砂糖は精製されていますから不純物がありません。それは酵母によって100%アルコールに変えられるということです。
そのため、「風味が変わらず」、「ドライでアルコール度数の高い」ビールにすることができる。買ってくるビールの原材料には砂糖は入っていませんが、発泡酒などビールタイプの飲料には、原材料に糖類が入っています。
もちろん、モルトが多くなると酒税法でビールになってしまうからです。
その分、アルコール度数は高めで、風味があまりない薄いビールのような味になりますね。飲むと分かります。なるほどなあと思います。
まとめ
この本は、変形B5版サイズでわりと厚い紙を使った254ページの本です。写真がかなり多く分かりやすいです。
ビール好きなら1冊持っておきたい本です。ビール好きに知らせるとたくさん売れるのではないかと思いました。まだアマゾンではレビューが1個しかついていません。
この本を読みながら、以前、かなりマニアックな発酵の技法 ―世界の発酵食品と発酵文化の探求を紹介したことを思い出しました。料理をオタク的に解説する本です。タイプが似ています。
このような種類の本はいままでなかったと思います。ネット時代になり、サイトで記事を公開していると人気が出て本になったのかもしれません。
今の時代、個人の興味は分散化していますが、その分、興味のある人は、より深く詳しい話を求めるようになっていると思います。
ビールについて他に書いた記事があります。ビールについて書いた記事をご覧下さい。